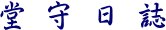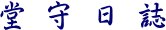2026/02/22 [日] 菅野完氏の2/21(土)朝刊チェック:高市早苗施政方針演説を冷徹に解剖する
|
五十六年前の田中角栄の施政方針演説との比較―その落差に、涙がでた。
|
2026/02/21 [土] PM2.5、or 花粉?
|
今日の昼食は、かねてから期待の中京「わたつね」へ。十一時開店で半過ぎに着くと、すでに五人の列。十分ほど待って、店内へ。海鮮丼1,800円+ライス大盛りを注文。
具には、とこぶしの煮付けやしらうお、白子がのっていて、それなりに楽しめた。次は、売りの手打ち蕎麦を食べに行きたい。
その後は、芸術センターに〈からだとことばを育む会〉のチラシを置き、フィンランド・パン「キートス」で予約していたパンを買い、二条駅前の生協でトイレットペーパーと納豆「りつまめ」――京都の納豆の中で、ベストでは?――を購入し、帰宅。
が、昼寝の後、起きてみると、体調不良に。人の多い中に出かけたためか、それとも空(気)が汚れていた、PM2.5、or 花粉のために、胸がシンドクなってしまったか・・・。
明日にそなえて、早く寝ることに。
|
2026/02/20 [金] トランペットの鐘/金が、高らかに鳴り響く
|
トランプ+ペット、タカイチの施政方針演説――官僚の作文、自分でも何を言っているのか無知・無能の人間には、分からないだろう。
|
2026/02/19 [木] 復旧
|
午後から業者が入って、工事。NTTの配線接続機器が劣化していたのが原因と分かり、交換。こちらの問題(自損)ではなかったので、無料になった。良かった。
※
夕方、ゲストハウスに六泊されるご夫婦が、長崎から来館。奥様が化学物質過敏症のため、京都旅行ができてとても喜んでくれた。手土産にいただいた長崎カステラを、おいしくいただく。
|
2026/02/18 [水] 好事魔多し
|
今朝は、久しぶりに寝たなあ〜、と目が覚めて「今日を一日、」と意気込んでいたら・・・掃除の後に、ふとメールをチェックしておこうとデスクトップのPCを立ち上げたら、何と! インターネットがつながらない。
ノートパソコンやスマートフォンのwi-fiも、アウト。このような場合は、電源の抜き差し(再起動)で解決することがあるので、何度が試みたが、事態は変わらず。もしやOCN側の問題ではないか、と予測して、設定マニュアルを探し出してサポートへ電話。
案の定、OCN(実際はNTT)の配線に不具合があるのではないか、ということになって、明日の修理につなげられた。
メールはスマートホンに転送設定してあるので何とかなるが、困ったのはエアレジが動かないこと。思案にくれた時、千晶がデザリングの経験を思い出して、菜芭にTEL。店まで来てもらって、スマートホンとエアレジ用のipadをデザリングでつないでくれた。
電脳社会では、インターネット回線や電気が、死活路だな、と痛感。もしもの時に備えて、代替を用意しておかなければ、と反省&改善点になった一日だった。
|
2026/02/17 [火] 基礎講習会
|
参加者1名。この機会に内観技法の基本の型を見直し、一)心眼→二)呼吸へと順序を代えたほか、元気の気のまわりを、静体では拡大or縮小に、動体では拡大or縮小+回転へと変更する。
来週は、基本の型で“福は内”&“鬼は外”を行い、からだの勘覚(気)の〈裏〉と〈表〉について話す予定。
|
2026/02/16 [月] 今日の一日
|
昨日の作業を続ける。
|
2026/02/15 [日] 今日の一日
|
「世間では、「基本は変えずに、応用を更新する」と言われているが、逆ではないか」と、整体の師が語っていた。何も応用を否定したのではなく―チャレンジを続けていれば、必然的に応用は自己変化を遂げる―基本にこそ更新のダイナミズムを求めたのだろう。
明日からの基礎講習会に備えて、〈内観技法の基本の型〉のプリントを―単に字面だけでなく、実際にからだで試しながら―作り直す。
|
2026/02/14 [土] 私たちの願いは―
|
めだかの鉢をかきまぜると、いったんは全体が濁るが、しばらくすると上の方が澄んでくる―底は泥がたまったままで。
私たちの願いも、そんなものではないか、と今朝、思った。欲望>欲求>願望>希求>いのり、の多層多重をなして。
|
2026/02/13 [金] 「革命は―」
|
明日からのゲストハウスの宿泊客の準備をしていて、思った。毛沢東が語った「客を招いてごちそうすることではない」を、逆転させよう。中国革命を全否定するのではないが、文化大革命で百万人以上が殺された事実を直視すれば――
「客をまねいてごちそうすることが、革命である」と。
|
2026/02/12 [木] え、社会学者は誰にも務まる?!
|
今朝の毎日新聞・朝刊に、選挙の結果に対する二人の社会学者のコメントが載っていた。その見出しが、「若者 リベラルを権威視」と「中道『左派』に見られた」。
両者とも、逆では?
|
2026/02/11 [水] 「フェアプレイはまだ早い」by 魯迅
|
選挙の結果を受けて、感想。“けたぐり”でも何でも、とにかくタカイチの野望――スパイ防止法・憲法改正(緊急事態条項&九条)――を止めること。
|
2026/02/10 [火] 日本の外交政策は、どうあるべきか
|
私は、鳩山由起夫・元首相が提唱している 東アジア共同体構想に未来(希望)をみるが、カナダのマーク・カーニー首相が1月20日、スイスで開催中の世界経済フォーラム(ダボス会議)で行った演説 “ミドルパワー・連合”も、一つの参考になるだろう。 「原則と現実主義:カナダの進む道」と題されたカーニー首相の演説の 英語原文& 日本語訳全文。 ※ かねてからの懸案だったゲストハウスの庭木〜石榴・ローリエ・無花果〜の剪定を行う。本来なら、去年の落葉後に行うべきだったが。次善の対処。 |
2026/02/09 [月] 元プロ野球選手・野村克也の名言「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」
|
朝二時間、普段は読まないアカウントも含めて、ツイッターで選挙の結果を自己分析。中道改革連合の敗北&自民極右派の勝利は、どちらも不思議なし。
デジャビュ(一)民主党・野田佳彦首相による自民党への政権委譲、(二)同じく民主党・前原誠司代表による希望の党への合流失敗、(三)“小泉劇場”以来の安部→高市と続く、自民党&メディアのイメージ戦略、(四)立憲・共産・れいわ・社民のリベラル派の分立状態、(五)アメリカによる陰に陽にのバックアップ。
But、タカイチの場当たり的な経済&外交政策のために、円安・国債&株価の下落→タカイチは、国内政治の失政をごまかすために、極右外交でポイントを稼ごうとするだろう。その時にリベラル派の統一戦線ができれば、まだ日本再生の道は、残されている。
|
2026/02/08 [日] 雪の投票日
|
朝、九時過ぎに会場の仁和小学校に向かう。吹雪が舞うなか、下の森通には誰も見えず。投票所は閑散かな・・・との予期は思いがけず裏切られ、混み合っていた。 ダメイチへの怒りが、良い結果につながれば・・・。 ※ 〈からだ学び 事始め〉「 第二稿」を、ホームページにupした。 |
2026/02/07 [土] 時間に支配されないために
|
ミヒャエル・エンデの『モモ』には、時間泥棒なる男たちが登場するが――時間に支配された現代文明への揶揄として――今おもいかえすと、母が自宅で療養していた時、ベッドに目覚まし時計を二つも置き、常に時間を気にしていた。
後に大腿骨骨折で入院し、起きられなくなって退院、グループホームに移って一週間で亡くなってしまった(看護師が常駐といいながら、ウソで劣悪な施設だった)。母は、残された時間を、確かめていたのだろうか・・・。
なるべく時計を見まい、と決めた。時間に支配されるのではなく、逆に支配する、というより時間にとらわれないために。こういうライフスタイルができるのも、自営業者のメリットだろう。
もう一つ、インターネットに時間を支配されないために、windowsパソコンにプリセットされているタイマーを活用している。5分、15分、30分、45分の4つで設定して、その都度、タイマーが鳴ったらそれ以上、見ない。
明日は投票日、そして明後日の開票と、時間の支配者が押し寄せてくるが、波に飲み込まれないように、警報発令。
|
2026/02/06 [金] 「ヒロシです」
|
一世を風靡したあのような自虐ネタではなく、自分(の言動)を笑いのタネに提供できるというのは、人間の成熟度のバロメーターだ。今日、千晶がスマホで共産党の衆議院議員候補・清水忠史氏の街頭演説を聞いていたのが耳に入ってきて、そう思った。
タカイチ一派には、逆立ちしてもできない芸当だろう。ないものねだりかもしれないが、今から思えば石破茂氏にも、また私がサポーターになっているれいわ新撰組代表の山本太郎氏にも、“笑い”が欠けているように感じる。
|
2026/02/05 [木] 「潮目が変わった」
|
という声を、聞く。そうあってほしい。タカイチ・ダメイチ・ウソイチ・ニゲイチを首相の位置に留まらせないために。
「打倒高市政権」を掲げて、一水会が街頭宣伝をしているのは――私とは天皇制に対する立場が真逆だが――心強い。後は、日曜日の天候が荒れ模様という予報で、投票率にどう現れるか?
|
2026/02/04 [水] 「一日一生」
|
今日も、ではなく、今日を。三十年前に室戸岬で出会った空心さんから贈られた、達磨さんの絵に「喝!」の色紙を想いうかべながら、毎朝、神棚で柏手をうっている。
※
スウエーデンのプライマリーケアの実態を、大使を務めた方が毎日新聞の朝刊に語っていた。市民がプライマリーケアセンターに連絡すると、3日以内に家庭医が診察し、その後90日以内に専門医の診察、さらにその後90日以内に専門医の治療が行われるルールが存在するという。そのため、「医療へのアクセスの抜本改善は国民の悲願」だという。
スウエーデンでは患者の自律意識が強いそうだが、日本政府がすすめている自助努力(病院にかかるな、市販薬でごまかせ)は、家庭医のシステムなどが調っていない日本では、患者切り捨てそのものだろう。
軍事費を、医療費などの社会福祉にあてよ。
|
2026/02/03 [火] 小遣い制
|
今までどんぶり勘定で、何をするにもレジからお金をとって使っていたが、二人で話し合って今月から小遣い制に改めた。一万五千円ずつ現金で“支給”し、そこから個人的に必要なもの―趣味や道楽―をまかなう。
私はwebでの本の購入や、外食費用(昼に、定食を週一で食べに行くのが楽しみ。一回1,300円程度)、春からはトレッキングの交通費もかさむ。千晶は、通販での服や本の購入、カフェでの飲食費にあてるという。外(スーパーやパン屋)で買って家で食べる食材や、伊丹への母の見舞い費用(交通費や食事代)は、除外。
店を畳んで仕事を辞め、年金生活オンリーになったら、こうせざるをえないだろう。そのための予行演習だと思えば、限られた金額でやりくりするのも、また一つの楽しみだ。
|
2026/02/02 [月] 義母の誕生日
|
御歳、九十八! 四人の親のうちで最も(体力的に)弱いと思われていた―早くから腰が曲がって、心臓にペースメーカーを付けていた――義母が、最も長生きするとは。人間の定めは、分からない。
一ヶ月ぶりに、西郷光太郎さんから連絡があり、電話で話す。声に力がなくなっていたが、声を聞けただけでもよかった。豆料理のリクエストがあってので、千晶が豆スープとサラダを作って送る、と約束する。
西郷さんも、医者からは(一昨年の秋に)「来春まで―」と言われたが、訪問看護やヘルパーの支援を受けて、自宅で闘病生活を続けている。胸の痛さ息苦しさは、オレにも分かる。この春に、京都まで桜を観に来てほしい。
|
2026/02/01 [日] 今日の一日
|
『らくてん通信』の校正&編集作業。NHKテレビの党首討論を、タカイチがウソ八百で逃亡。夜7時のNHKニュースがどう報道するかと思ったら、香港での窃盗事件がトップ。後々に、「タカイチは、日曜討論の出席を見送りました」とコメント。
公共放送ではなく、自民党広報局。
|
| |